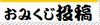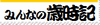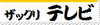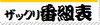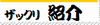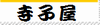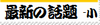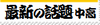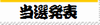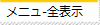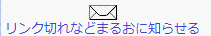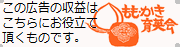gakushu - 最新エントリー
(NHK20140518)
大黄の根が黄色なので大黄という名前になりました。
別名「将軍」の名があります。
国を治める内政には、国老(家老)が働き、
外政に対しては将軍が担当するもので、
国を病気に置き換えて考えます。
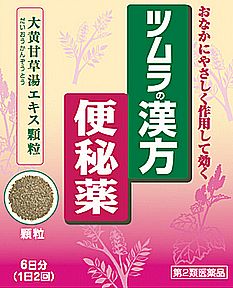
病気を治す薬にも国老と将軍があり、体内でのアレルギー反応を抑え、
体内からの病気になるものを防ぐ国老に相当する働きの薬と、
積極的に病気の因に対して働く戦いをしようとする、
将軍のような働きがあります。
国老の働きは甘草、将軍の働きは大黄が行うため、
大黄は別名、将軍とも呼ばれています。
言うまでもなく大黄は中国で開発された世界的な薬物です。
既に紀元前からはるばるシルクロードを経てヨーロッパに伝えられ、
わが国でも古く奈良時代の文化の遺産である正倉院(756年)の
薬物の中にも大黄が現存することは周知の通りです。
広い中国では大黄の品質も多種多様のものが出回っています。
大黄の原植物はその生産地によって相違します。
(NHK20160603)
(TBS20160917)
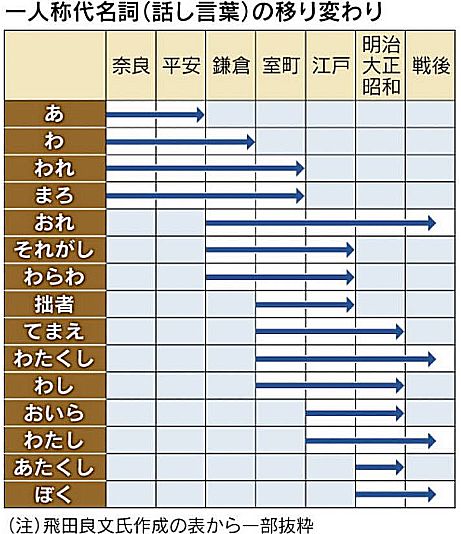
(TBS20140902)
古代、この周辺の地域にはウェネティ人が住んでいましたが、
4~5世紀のゲルマン民族移動で追われた西ローマ帝国の難民が
この湿地帯へと避難してきたことから、
452、ベネチアの歴史が始まりました。
足場が悪い湿地帯のため、侵入者は追ってくることが出来ず、
避難した人々はここに暮らし続けるようになりました。
アドリア海沿岸地域は元々東ローマ帝国の支配下にあったため、
名目上は東ローマ帝国に属しましたが、実質的には自治権を持っていました。
697、ベネチア人は初代総督を選出して独自の共和制統治。
810、フランク王国が侵攻、ベネチアとの交易権を獲得。
詳細→YouTube:Taberu Travel
イスラム諸国とも交易を拡大、
東ローマ帝国とは貿易特権と引き換えに海上防衛を担当。
1104、軍直属の軍需工場が創業。
1320、軍船や大型商船の造船所となり、最大1万6千人が従事。
1370、その後は銃器も生産され、
16世紀には世界における造船・兵器製造の一大拠点となりました。
(TV朝日20140426)